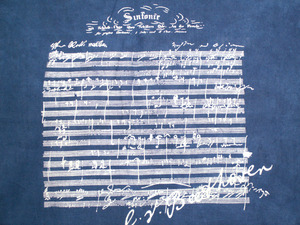今日は、その内のひとつ、付下げの下絵が描けたとのご連絡を頂いて、
お客様と佐伯さんに再び弊店でお出会い頂き、細かなご相談をしました。
佐伯さんは、実寸大に紙に描いた下絵を持って、朝早く、京都の北区のご自宅からお越しくださいました。
その下絵を体に巻きつけて、
「柄の大きさ、量、裾からの高さ、いかがですか?」

「前袖には、桜の柄を置きました。」
2度、3度裾線を折りなおして当ててみて、ベストポジションを決定しました。
次は、地色です。
「クリーム色とのご希望でしたが、どの色がお好みですか?実際に肌に当てて見てくださいよ。」
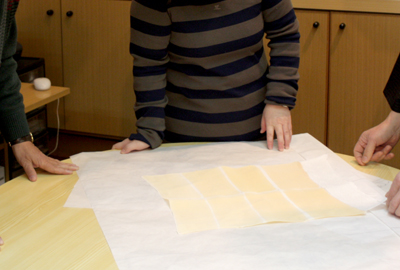
「プロの大先生にお任せします・・・
 」と仰いながらも、やはり
」と仰いながらも、やはり「これが好きかな~」と、選ばれると、
「ああ、私もその色が良いと思っていました。」
「この花は、どんな色を挿すおつもりですか?」
「地色を染めて、柄を描き出すと、いいアイディアが浮かぶものなので、
事細かには決めてしまわない方が良いのですが、ここはグレーとかはいかがです?」
「なるほど!いいですね!!
 」
」こうして一時間近くご相談されて、お客様は満足されてお帰りになりました。
ずいぶんと、熱心に、丁寧に・・・・と思っていましたが、
「別染をする、ということは、お客様の気持ちを汲むことが何より大事なんです。
この段階を、きっちり押さえておくことが大切だと思っています。
クリーム色を選ばれるときも、どの色と迷われているのか知るのと知らないのとでは違います。」
「せっかく別染するのです。『着物に着られる』という言い方がありますが、出来合いの着物を、
どこか自分を着物に合わせて着るのではなくて、この着物をすべてご自分が支配する感じでお召し頂きたい。」
佐伯さんのものづくりの心に触れて、とてもありがたく、
こういうお手伝いができる店だということに誇りを感じ、さらに、がんばらなくちゃ!!と思ったのでした。



 夕方から荷物を出すにも、帰りの駐車場に行くにも、、車を出すにも・・・・・・・・・
夕方から荷物を出すにも、帰りの駐車場に行くにも、、車を出すにも・・・・・・・・・ !!今夜は満月の皆既月食だった!!!!!と物干しに出て、月を眺めました。
!!今夜は満月の皆既月食だった!!!!!と物干しに出て、月を眺めました。







 だったのですが、バーの位置が低くて、イマイチ恰好が良くない・・・
だったのですが、バーの位置が低くて、イマイチ恰好が良くない・・・



 なんだけどな~・・・・・・
なんだけどな~・・・・・・